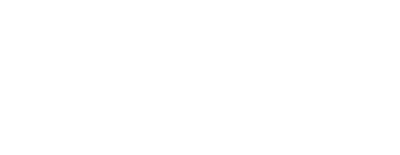「余白って、なんですか?」
ものづくりと向き合う時、おそらく全ての作り手が強烈に意識させられるものがあります。
それが、「余白」です。
私自身、装飾を削ったり、構造を簡素化したり、そういう判断をしてきた自覚はあります。
でも、それは「余白」の表面、入り口に過ぎません。
「余白って、なんだろう?」
見せないから、見えてくるもの
ランプシェードという製品は、光を“見せる”装置であると同時に、
光を“遮る”装置でもあります。
その矛盾を抱えたまま、私たちは設計を続けています。
布や和紙を使えば、そこに表情は生まれます。
でも、表情を強くしすぎると、今度は空間の主張になってしまう。
だからこそ、どこかに「余白」が必要だったのです。
布の透け感、骨組みの細さ、コントラストの控えめさ──
それらをすべて“引きすぎない”ギリギリで設計していく。
結果として、「気づかれないけど、なんとなく居心地がいい」照明ができあがっていく。
たぶんそれが、私たち作り手にとってのわかりやすい「余白」の一面です。
足すよりも、引く勇気
製品開発をしていると、つい“足したく”なります。
パーツを増やす、色を足す、装飾を加える。
でも、そのたびに違和感も少しずつ膨らみます。
「あれ、ちょっとくどいな」
「空間の中で浮いてしまうな」
「悪くはないけど、“自分で主張してる”気がするな」
そういう製品は、結局あまり長くは売れませんでした。
逆に、「物足りないかもしれないけど、落ち着く」製品が、気づけばずっと残っている。
“引く”という判断は、難しいものです。
でも、照明のように空間と共にある製品にとっては、
「自分が語りすぎない」という姿勢こそが、結果的に“長く使える”条件になるのかもしれません。
壊れないという「余白」
もうひとつの「余白」は、見た目ではなく、使い心地の中にあります。
それは──「壊れないこと」。
もちろん、どんな製品でも、壊れないように設計するのは当たり前です。
そして、どう設計しようと結局は必ず壊れます。
私たちが目指してきたのは、もっと身近で、微細なレベルでの「壊れなさ」です。
たとえば、照明が少しずつ傾いてくる。
コードがねじれてしまう。
ビスが緩んで音がする。
布が湿気で浮いてくる──
それらは、スペック上は“壊れていない”。
でも、使う人にとっては、ちょっとした“煩わしさ”になります。
だから私たちは、こういうストレスが「起きない」ように、
設計や素材の選定を微調整してきました。
壊れると、煩わしい
照明というものは、普段あまり意識されない存在です。
点けたときにきちんと点いて、空間を照らしてくれる。
それだけで十分──そう思われがちな存在です。
けれど、ひとたび壊れると、照明は“即座に不便”になります。
パーツがずれて傾いている、
布が剥がれかけている、
そして、スイッチを入れても光らない。
──それだけで空間の機能は決定的に損なわれ、使う人にとってのストレスになります。
私たちが「壊れにくさ」にこだわるのは、
そうした煩わしさを“ゼロ”に近づけたいからです。
決してゼロにはなりません、それはわかっています。
ですが、ゼロに向かって作られたものは、無頓着に作られたものと圧倒的に違うはずです。
すこしでも傾かないように、
どれだけ使ってもズレが出ないように、
温度変化や湿度に耐える構造になるように。
そして、いつまでも灯るように。
それは華やかでも、目立つ部分でもありません。
でも、壊れないことで“思い出されない”存在になること──
それこそが、私たちの考える快適さのかたちです。
「壊れないから、気にしなくていい」
──その余白が、暮らしにとっては案外大きいのではないでしょうか。
記憶に残らない「良さ」を、つくる
「この製品、何も気になるところがないですね」
──これが、目指すところです。
なぜならそれは、“壊れていない”ことにも、気づかれていないということだから。
快適さや心地よさは、しばしば“無意識”の中にあります。
違和感がない、使いにくくない、触れていて安心できる。
そのすべては、「これといって印象がない」にも似ている。
でも、使い続けるうちに、「結局これがいいよね」と戻ってきてもらえる。
「なぜかあれが好きだった」
「気がついたら、そればかり使っていた」
そういう“記憶に残らない良さ”を、私たちは「余白」と呼んでいます。
お問い合わせがないという幸福
長く愛用されている商品には、特徴があります。
お問い合わせが極端に少ないことです。
説明書を読まなくても分かる。
何も考えずに設置できる。
点けてすぐ、「これでいい」と感じられる。
そして、何より不具合が無い。
設置したが最後、十分に長く寿命を全うするまでの間、ほとんど意識を向けることがない。
製品が「余白」を持っているからこそ、
使い手がそのまま、暮らしに自然に溶かし込んでくれる。
「困ったことがない」というのは、作り手にとって、見えないけれど確かな信頼です。
「ない」をつくるために、「ある」にこだわる
もちろん、「何も起こらない」という状態は、偶然ではありません。
それをつくるために、実はたくさんの「ある」にこだわっています。
・フィルムの厚みを0.05mmだけ変える
・電球の交換時に手を入れやすい距離を計算する
・コードの引っ張り角度によってテンションがかからないように固定パーツを調整する
そんな微調整の積み重ねが、「気にならなさ」を生んでいる。
誰にも気づかれない努力が、「余白」というかたちで残っている。
「なくてもいいけど、あってよかった」
20年製品をつくってきて、ようやく気づいたことがあります。
私たちが届けたいのは、「主役」ではなく、
「なくてもいいけど、あってよかった」と思ってもらえる存在なのかもしれない、と。
何も語らず、空間のなかに静かに佇んで、
ただそこで、光を受け止めている。
──それが、私たちの考える「余白の価値」です。