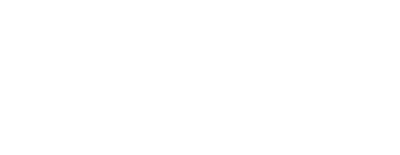20周年連載 第3回|『修理』作り手の構え「製品が“続いていく”ということ」
製品は、終わらない
あるとき、10年前に納品したお客様から、久しぶりにご連絡をいただきました。
「コードが切れてしまったのですが、修理してもらえますか?」という問い合わせ。
正直、少し驚きました。
というのも、その製品はすでにカタログからも外れていて、部品も今の仕様とは違っていました。
でも、たしかにその製品は、私たちがつくったものでした。
手元にあった古い設計図を引っ張り出して、コード径と接続方法を確認し、可能な限りの方法で修理を施しました。
そのとき改めて思ったのです。
「ものづくりって、“終わり”がないんだな」と。
納品された後に始まる時間
製品は、完成した瞬間から、少しずつ変化していきます。
光の熱で布地の色がほんのわずかに変わったり、設置環境によってフレームに微妙な歪みが生まれたり。
でもそれは、「劣化」ではなく、「馴染み」だと私たちは思っています。
暮らしの中で、少しずつ空間に溶け込んでいく。
使う人にとって、だんだんと「当たり前の存在」になっていく。
それは、製品としての“完成”とはまた別の、「付き合いの時間」のようなものです。
そしてその時間の中で、思いもよらない出来事が起きたりします。
地震で落ちてしまった。子どもが触って壊れてしまった。照明の規格が変わった──。
そのたびに、製品は問い直され、形を変え、そして、続いていく。
「使い捨てない」という選択
私たちの製品は、決して安いものではありません。
量産もしていないし、材も工程も、どれも手間がかかっています。
でもだからこそ、「壊れたから終わり」にはしたくなかった。
むしろ、「直して使い続ける」という選択肢を前提に設計したい。
──それが、初期からの私たちの考え方でした。
初期モデルの一部には、メンテナンスを想定していない構造もあり、対応に苦慮したこともありました。
でも、お客様とやり取りする中で、私たち自身がその製品を“学び直す”機会にもなりました。
「この部分、次からは交換しやすいようにしよう」
「こういう設置だと、引っ張りに弱いんだな」
そうやって、設計は少しずつアップデートされていきました。
製品だけでなく、考え方ごと。
完成してからの「フィードバックの蓄積」が、ものづくりそのものを変えていくのです。
「完成形」は、固定されていない
ときどき、「あのときのモデル、今も手に入りますか?」というご連絡をいただくことがあります。
もちろん可能な限りお応えしていますが、厳密に“当時とまったく同じもの”をご提供できるとは限りません。
素材の仕入れ先が変わったり、微細な寸法が見直されたり、塗装工程が少しだけ変わっていたり。
でも、それは「妥協」ではなく「進化」だと思っています。
私たちにとっての「完成形」は、ひとつではありません。
むしろ、使われ、壊れ、直され、また使われる中で、少しずつ書き換えられていく。
そんな「更新可能な完成形」があるのだと、今では思えるようになりました。
修理は、ものづくりの続きだった
今では、「修理」という行為を、ただのアフターサービスだとは思っていません。
それは、製品をもう一度「触る」機会であり、
つくったものと、再び向き合うチャンスでもある。
お客様のもとで、どんなふうに製品が使われ、
どんな経年があり、どんな不便があったのか。
それを知ることは、私たちにとって大きなヒントです。
時には、想像を超える使い方をされていて、
「なるほど、そんな環境で生き延びてたのか」と思うこともあります。
修理を請け負うことは、「完成したもの」に戻ることではありません。
むしろ、「これからも続けるための、次の一歩」に触れること。
完成は、終わりではなく、通過点。
その先を一緒に歩くように、製品と付き合っていく。
それが、私たちの考える「続ける」ということです。
「直す」ことにも、美しさを
最初のころ、修理は“やむをえず行う作業”のように感じていました。
壊れた箇所を直し、使える状態に戻す。
──それだけで、十分だと思っていたのです。
けれど、実際にやってみると分かってきました。
修理という行為にも、「つくる」と同じくらいの手間と選択があること。
そしてそれは、私たちの“姿勢”がもっともよく現れる場面でもあること。
たとえば、コードの取り回しひとつ取っても、
どう結線すればテンションがかからないか、
交換部品を使うとき、元のデザインとの調和はどうするか、
あえて「違い」を見せる修理にするか、それとも「気づかれない」ように仕上げるか。
修理には、そうした細部の判断がいくつもあります。
単に「元に戻す」のではなく、
その製品がこれからも“暮らしに溶け込めるようにする”という視点が必要なのです。
時間を受け入れるための手仕事
ときには、「どうしても元の部材が手に入らない」ということもあります。
その場合は、同等以上の材を探し、強度や質感を照らし合わせて慎重に置き換えます。
そうやって手を入れながら、私たちはその製品の「これまで」を知っていきます。
「ここはたぶん、よく触っていた場所だな」
「この色の変化は、南向きの窓のせいかも」
修理の途中で、そうした“時間の痕跡”と向き合うことがあります。
それは、とても静かな、でも確かなコミュニケーションです。
そして私たちは、壊れる前よりも、少しだけ“良く”なるように仕上げたいと願います。
補強を加えたり、塗装を一部やり直したり。
元に戻すだけではなく、「これから」に耐えられる状態へと仕上げていく。
それは、時間を受け入れながら、手をかけて続けていくということ。
「長く使ってもらう」という言葉の、もう一歩奥にある覚悟だと、思うのです。