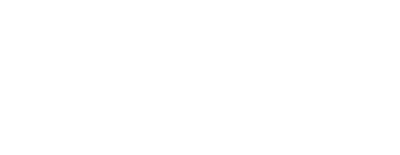20周年連載 第2回|「“顔”のある誰かと出会う──展示会が教えてくれたこと」
Webで伝えられなかったこと
製品ができたとき、最初にやったのは、Webに載せることでした。
写真を撮って、説明文をつけて、サイズや価格を整えて。
「きちんと伝えれば、きっと届く」と思っていました。
ありがたいことに、そのWebサイトをきっかけに、製品について“読んでくれる”人は少しずつ現れてきました。
素材や工程についての質問をいただくこともあり、言葉や写真がちゃんと届いている実感もありました。
けれど、どこかに“もう一歩”の距離を感じていました。
たとえば、ランプシェードの内側で光がにじむ感じ。
布越しに見えるフレームの陰影。
手に取ったときの重さや、柔らかな質感。
──そうした細部の「生々しい手触り」が、どうしても画面越しには伝えきれていないように感じたのです。
どんなに丁寧に書いても、どれだけ美しい写真を使っても、どこか“平べったい”。
Webの向こうには「誰か」が確かにいるはずなのに、その誰かが、やはり遠く感じられる。
“読んでもらえた”という手応えがあったからこそ、「読む」から「触れる」への距離の大きさに、はじめて気づいたのかもしれません。
初めての展示会出展
「直接見てもらう場が必要だろう」
そう思って、はじめて展示会に出ることにしました。
といっても、大きなブースなんて出せるわけがありません。
会場の端の、小さな一区画。
什器は全部DIY。
照明は家で使っていたスタンドをそのまま持ち込み、タコ足配線に不安を感じながらの初出展でした。
前日は眠れませんでした。
何を言えばいいのか分からない。
立ち止まってくれる人なんているのか。
「誰も来なかったらどうしよう」──そんな気持ちで、朝を迎えました。
目の前に現れる“見てくれる人”
けれど、会場が開いてしばらくすると、少しずつ人がブースの前で立ち止まってくれるようになりました。
黙ってじっと製品を見つめる人。
「これ、どこで作ってるんですか?」と聞いてくれる人。
「うちの照明器具に合うかも」と、スマホの写真を見せてくれる人。
どれも、Webでは出会えなかった人たちでした。
中には、私たちがまったく意図していなかった視点で製品を見てくれる方もいました。
「この素材、うちの医療機器でも使えそうですね」と言われたときには、本気で驚きました。
作っているときには気づかなかった可能性が、他人の目によって初めて見えてくる。
そんなことが、何度もありました。
「売る」ことじゃなかった
初めての展示会で、製品は一つも売れませんでした。
でも、不思議と落ち込みませんでした。
「売れなかった」のではなく、「出会えた」から。
出展から数日後、展示会で名刺を交換した方から、メールが届きました。
「実物を見たから、検討できます」
「また次、違う色が出たら教えてください」
そのとき思ったのです。
展示会は、売る場所じゃなくて、出会いの“予告編”だったんだと。
他者の目で、製品が変わっていく
展示会のあと、製品を少しだけ作り変えました。
布の透け具合を調整して、土台の高さを5mmだけ変えました。
それは、あのとき、無言でランプを見つめていた人がいたからです。
その目線の高さ、その立ち位置、反応の“間”。
言葉ではない情報を、私たちは受け取っていた気がします。
製品は、自分たちで作っているようで、
実は、誰かとの関係の中で、少しずつ変わっていくものなのかもしれません。
出展していなかったら、気づけなかったことばかりです。
完成は、私たちの手の外にある
納品は、終わりじゃない
初めて製品を納品したとき、
それは「完成」だと思っていました。
部品を作り、組み立て、梱包し、納品書をつけて送る。
そこまでやって、ようやく一区切り──そう思っていました。
でも、実際には、そこからが始まりでした。
数週間後、お客様から写真が届きました。
製品が、部屋に設置されている写真。
私たちの手を離れたその照明が、
ある暮らしの中で、当たり前のように光っていたのです。
そのとき、初めて「完成は、工房の中にはない」と知りました。
設置という“翻訳”
納品先によって、設置の環境はまったく違います。
天井の高さ、壁の色、窓の位置、床材の反射率。
同じ製品でも、まるで違って見える。
中には「ちょっと暗く感じました」と言われることもありました。
あるいは、「思ったよりもあたたかい光で驚いた」と言われることも。
設計通りのスペックであっても、
設置環境が変われば、意味が変わる。
──製品は、場所に応答して“翻訳”されてしまうのです。
だからこそ、納品前に「何を伝えておくべきか」は、いつも悩みます。
光源の色味、取付部の仕様、設置位置の“おすすめ距離”……
でも、すべてを伝えることはできません。
むしろ、伝えきれないからこそ、信頼が要る。
仕上げてくれるのは、使う人だった
あるとき、旅館に納品した照明が、
想定とはまったく違う高さに設置されていたことがありました。
「えっ、そんな使い方!?」と思うような位置。
でも、見てみると、妙にしっくり来ている。
むしろ、こっちの方が“正解”だったんじゃないかと思うほどに。
あとから聞くと、
「そこの柱がちょうど空いてたから」「お客さんの背の高さに合わせた」とのこと。
──私たちが決めた“設計”は、
現場で、暮らしの中で、“運用”によって再編される。
そのとき、製品は初めて“仕上がる”のだと気づきました。
「完成」を手放すということ
ものづくりをしていると、つい、「完成」にこだわりたくなります。
細部の寸法、仕上げの質感、梱包の形。
どれも、きちんと届けたい。妥協したくない。
でも同時に、「自分たちの完成」と「相手にとっての完成」は違うということも、だんだん分かってきました。
私たちのつくったものは、
どこかで誰かの手に渡り、
誰かの場所に置かれ、
誰かの視線と暮らしの中で、静かに馴染んでいく。
そこで見せる顔こそが、その製品の本当の「完成形」なのかもしれません。