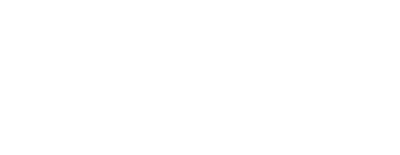20周年連載 第1回|「抱える」という選択が、作り手にしてくれた
1. 製品の「裏側」から始まった独立
―― フィルムという“裏方”が、すべての始まりだった
弊社が初めて本格的に自社製品を作ろうとしたとき、最初に直面したのは「フィルム」でした。
ランプシェードの内側に貼る、耐熱性と防汚性を備えた透明なフィルム。
製品の“顔”にはならないけれど、これがなければ、形にすらならない。
この素材がどれほど重要かは、当時すでに明らかになっていました。
私が業界に入った2000年前後、布や和紙の裏にフィルムを貼るという技術は、
もはや一部の応用ではなく、ひとつのスタンダードとして定着しつつありました。
それまでの伝統的なランプシェードは、繊細な布や紙そのものを構造体として用いるものでした。
当然、湿気や熱、汚れに弱く、製造も熟練の技術を要し、扱いも難しい。
そこに、フィルムを裏打ち材として貼るという発想が導入されたことで、
製品の堅牢性・耐久性は飛躍的に向上し、作業性も格段にアップしました。
結果として、製造の再現性が高まり、メンテナンスもしやすくなり、
ある意味では「伝統」を、現代の暮らしに接続可能な技術として延命させる素材でもあったのです。
けれど同時に、それは新たな課題も孕んでいました。
貼りたい布に、貼りたい形で、貼れるフィルムが、ない。
耐熱温度、厚み、粘着の相性、光の透過率、静電気、価格……
一つとして「これでいける」と言い切れるものがなかったのです。
だからこそ、私たちが製品を作る以前にまず向き合わなければならなかったのは、
この「裏側の素材」、フィルムとの関係でした。
2. フィルムの悩み
―― “ちょうどいい”が、どこにもなかった
市場には本当にさまざまなフィルムが出回っていました。
けれど、どれも“ちょうどよくない”。
粘りが強すぎて加工のときに手にくっつく。
静電気を帯びて、埃を寄せ集めてしまう。
接着剤がうまく定着しなくて、すぐに剥がれる。
素材名で言えば、PET、PP、PS、ABS……
それぞれに特徴はあるけれど、「これ一枚でいける」という素材には出会えませんでした。
高品質なものもありました。
デュポン帝人製の帯電防止フィルムなんて、性能的には申し分ない。
でも、そのぶん価格が跳ね上がる。
「使えるけど、使えない」──そうして、何枚かはそのまま棚に残ることになりました。
実際、当時の工房の棚には、
「これはいつか使えるかもしれない」という未使用のフィルムが何種類も積み上がっていました。
どれも“惜しい”けれど、“決定打”じゃない。
そんな状態が、しばらく続きました。
でも、その過程で得た知見をもとに、
私たちは試行錯誤を重ねて、最終的には自社オリジナルのフィルムをレシピから発注するようになりました。
加工性、耐熱性、接着性、光の透過率……
すべてを総合的に調整した、その素材こそが、
今では業界のスタンダードとして広く流通しています。
……レシピは、秘密です。笑
3. 決めない、でも抱える
――「余白」を棚に置いておくという選択
どれか一つに決める。
それは、ものづくりにおいてよく求められる態度です。
でも、フィルムに関しては、どうしてもそうはできませんでした。
加工性はいいけど粘りが強い、
帯電防止は効くけど価格が合わない、
薄くて軽いけれど接着剤がのらない……。
一長一短のある素材たちを前に、
私たちは「どれかに決める」のではなく、
「使い道がまだ見えていない素材を、とりあえず棚に置いておく」という選択をしました。
高価なフィルムもあれば、性能が過剰なものもある。
でも、「いつか、どこかで、誰かが必要とするかもしれない」。
そんな気持ちで、少しずつ素材を抱え込んでいったのです。
効率的とは言えません。
でも、そこに生まれたのは「在庫」というより、余白だったのかもしれません。
製品が生まれる前に、問いが立ち上がるための、空間としての在庫。
4. 在庫が生んだ関係
―― 必要とされるということの、別のかたち
「仕入れる」「抱える」「保管する」。
これだけを見ると、単なる物流の話に思えるかもしれません。
けれど、実際はもっと別の意味があったのです。
ある町工場では、材料ロットが大きすぎて持て余してしまう。
ある工房では、接着や加工の相性が悪くて使えない。
それでも、素材そのものが悪いわけではない。
ただ、“使いどころ”がない。
あるいは、“今”はない。
でも、だからこそ、それを一度受け止めておく誰かが必要になる。
私たちは、気づけばその「誰か」になっていました。
実はこの在庫を持つ、というスタイルも、
業界の先輩に言われた一言から始まりました。
「お前さ、このフィルム、抱えとけよ」
正直、最初はちょっと不満でした。
「なんだよ、それくらい分けてくれてもいいのに」って。
どうしてこっちだけが負担するんだろう、って。
でも、今になって思います。
あれは負担を押しつけたんじゃなくて、場所を与えてくれていたんだと。
役割を渡されることで、ネットワークの中に自分の居場所ができる。
その素材を抱えることで、誰かにとっての“頼り”になれる。
そうやって、必要とされるかたちが、自然に生まれていったんだと思います。
5. 作る前に、受け入れる
―― 素材を選ぶのではなく、素材に選ばれるように
「好きな素材を選べる」というのは、とても自由なように見えます。
でも実際には、その前に「選べない素材」をたくさん抱えてきたからこそ、
選ぶ目が育っていったのだと思います。
すぐには使えないかもしれない。
けれど、どこかに意味がある気がする。
そんな素材と向き合い続けてきた日々が、
少しずつ、ものづくりの基礎を形づくってくれました。
私たちにとっての「独立」とは、
製品を売り出した日でも、会社を登記した日でもなく、
素材に対して、腹をくくって向き合いはじめた日だったのかもしれません。